個人的に色々あり、新しい記事を載せるのが遅くなりすいません。
さて、前回は日本における箔の接着方法を、「平面美術(絵画)」と「立体物(建築含む)」に分けてお話ししました。今回は西洋、いわばヨーロッパの話です。とはいえ、大きく「ヨーロッパ」とはいいますが、私自身ベルギーで勉強して始めて知った技法もあるため、おもに「ベルギーの」と思っていただけるとよいような気がします。
私自身がベルギーの大学で学んだ人なので、「ベルギーは」はおおよその話として話すことができても、それを拡大解釈として「ヨーロッパは」と言うことにためらいがあるからです。
とはいえ「構造的考え方」としてはヨーロッパ美術における構造はおおよそ同一であると考えるといいと思います。
「この前置きの曖昧さはなんなの?」と思われそうですが、これは勿論「ヨーロッパ」というのはひとくくりにするには広すぎる場所だからです。「日本」と限定した場合でも、沖縄と北海道では地域差があり(ここまでの場所の違いを言わずとも、同じ県内でも市によって考え方が違うとか、隣県同士で文化が違うとかも普通にあると思います)、文化が違い、そこにある動植物が違い、生活が違う。
古い時代ほど「遠方の地域のもの」は手に入りにくく、高価になる(昔は「胡椒」が黄金的な価格だった時代もありました)。だから多くの場合は地産地消的に「地域の植生の(その地域で容易く手に入る)もの」を使用する傾向があります。使用する「もの」が違えば、その使い方やレシピ、活用法などが変わるのは料理などでも同じなのでそこはご理解いただけると思います(料理でも、同じ白い粉でも「小麦粉」「米粉」「かたくり粉」などいろんなものがあり、それらを使った似通った「揚げ物料理」があっても、その使い方、レシピ、活用法が違う、と言えばお分かりいただけるでしょうか)。そういう意味での相違はある、でも、構造としての考え方はヨーロッパではおおよそ同じな感じ、ということが言いたいのです。よろしくお願いします。
技法材料に関してお話しする前に、ヨーロッパで金箔を使用する際にそもそもにどのような基底材が用いられているのかということは重要なカギです。
西洋絵画の場合、金箔技法が使用される基底材になるのはおおよそ板(木材)となります。あるいは「絵画」に限らない「絵」がつくものですと「羊皮紙」なんかも挙げることができるでしょう(紙や印刷の出現以前は、本は羊皮紙の上に手書きされ、彩色された絵などもついていたからです)。もちろん近現代に近づくと画布(主に亜麻)を絵画の基底材としたものに金箔が使用されたりもしますが、これはある種例外的、といえるかもしれません。
立体的なものに関しては、彩色彫刻、ドールハウスのような西洋仏壇のようなもの、額縁みたいなものが例としてはぱっと挙げられます。金箔技法を使う古典作品において、一般的にはこれらの基底材は木であることが多いように思います。
加えて不動産(建物、道路などの地面)を基底材とする場合はそういった建物の建材あるいはフレスコのような素材を視野に入れるべきでしょう。フレスコは専門ではないので古典のフレスコの場合はどうなんだろう…ではあるのですが、ベルギーのアールヌーヴォー頃のフレスコの場合は金箔(あるいは金箔に見えるような箔類)が使用されているためです。
さて、ここまで見てきたところで金箔を使用する西洋絵画の基底材の多くが「硬質」であることに気づきます(羊皮紙は日本の日常で見るものでいうとスルメ、エイひれのような硬さがあり、紙や布のようなしなやかさは持ち合わせていないため、悩ましいですが硬質としています)。古典では画布上に金箔はほぼ使用せず、時代として19世紀末とか20世紀とかに入って画布上にも金箔の使用が結構でてきたのでは?と思われる感じの使用量です。これには「金箔を使用する意味」の違いがあるためと考えます。
この「基底材が硬質」ということが西洋美術における金箔のありかたにおいて関わりがあるように個人的に思います(あくまでも学術的な話ではなく個人的に、です。なのでもし学生さんが当記事を読んでいる場合、こういうブログの記事を参照に、レポートとか卒論を書く意味は全くないですよ~)。
上記にて、西洋美術においてどのような基底材上に金箔が使われているのかを書きましたが、では題材としてどのような作品に一般的に金箔が使用されるのか。
伝統的には「宗教」関係です。
有名どころですと13,14世紀のイタリアの板絵なんかを調べて頂けるといいですが、金箔をこれでもか!と使っているんですね。これにより現実世界との乖離(非現実性)や聖性、光り輝くまぶしい世界のようなものを表現しています。このきんきらきんな感じ…なにかを彷彿とするなぁと考えてみると、日本のお仏壇に似ているような気がします(苦笑)。まぁ、これに限らずヨーロッパの多翼祭壇画なんかも、お仏壇感いっぱいだったりします。国が全然違うのに、こういう似たり寄ったりを見ると、面白いなぁと思うんですよね(^^;)。
とはいえ西洋の宗教画において、いつまでも、そしてどこの国や地域でも画面いっぱいに金箔が使用されるわけではありません。額縁の部分限定だったり、聖人などの後光やお洋服の模様に少量、だったりもします。
こういった金箔使用の西洋絵画の時代性を見てみると、13世紀くらいから15世紀が多く、その基底材はほぼ全部板であることがわかります。勿論16世紀以降に基底材が板である作品がゼロというわけではなく、同時に金箔使用の作品もゼロというわけではありません。
とはいえ、技法材料的な視点で考えると基底材(板)と金箔の親和性というのが見えてきます。
これはなぜかといいますと、西洋絵画の場合の金箔の利用においては、金箔の性質を非常によく利用しているためです。この金箔の性質とは、「①展性」、「②腐食のしにくさ」、「③適正な技法材料による固着の良さ、および固着後の美観の整えやすさ」そしてこれは金属に共通することかとは思いますが「④磨くと鏡面様になる」ことです。
②以外はある程度の説明が必要になると思うので、先に②だけ簡単に言いかえると、錆びたり変色したりがしにくい、ということです。単純にキラキラ光る金属箔を求めるなら、例えば銀箔なんかも思いつくかと思いますが、銀箔は短期間で黒く変色します。他の昔から使用される身近な金属ですと「鉄」や「銅」なんかもありますが、これらは錆びたり変色しやすい金属です。宗教画のように「神の永遠性」を示す必要のあるもので、簡単に錆びたり変色したりして、そのキラキラを失う素材というのは美観としても作品の保存上としても適正ではありません。
さてそういう「腐食性」に関してお話しすると必ず「こういう金属もさびにくいし、変色しにくいからこれでもいいじゃない?」というご意見がでてくると思います。例えば金と系統の似た色調を持つ真鍮なんかがそうです。
しかし真鍮は箔として使うには使い勝手が悪いんじゃないだろうなあと思うのです。特に金の持つ「展性」みたいなものはないでしょうし、西洋の金箔技法を成り立たすことはできなかったんじゃないかな、と。まぁ特性一つだけの問題ではない、ということです。
ここまですでに結構長く書いていますので、本日はとりあえずここまで。このテーマで少々続きますので以降も読んでいただけましたら嬉しく思います。また、今回はこの記事を最後まで読んで下さり、ありがとうございます。ではでは、また~。







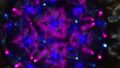
コメント