この記事のタイトルとおり、西洋美術での金箔の使用方法と技法に関わるお話しの2回目です。前回の記事の続きですので、先に前回の記事を読んでいただけると話が分かりやすいかと思います。
さて、前回の記事において、西洋絵画の場合の金箔の利用においては、金箔の性質を非常によく利用しており、その金箔の性質とは、「①展性」、「②腐食のしにくさ」、「③適正な技法材料による固着の良さ、および固着後の美観の整えやすさ」そしてこれは金属に共通することかとは思いますが「④磨くと鏡面様になる」であるとお話ししました。また、②についてはすでに前記事にてお話ししています。
ということで本日は他の3つの性質についてお話しします。②以外は、それぞれ独立した特徴ではなく、関わり合いのある特徴になるので、その旨ご理解いただけたらありがたいです。また、この②以外の特徴は日本画や本、巻子本など、紙や布を基底材とした日本の文化財における金箔利用とは違う部分となります。
さて、さっそく特徴④の「磨くと鏡面様となる」に関してですが、これを考える際に、そもそも「鏡」特有の特徴はなにか?と考えると、「虚像をうつす」ことや、「太陽などの光を反射して照らし返す」ではないかと思います。
では上記の「鏡面の特徴」はどうして発生するかというと、鏡の表面に当たった光のほぼ全てを反射するから、と物理の話では言われます。
ここでなぜ物理や光の話…と思われるかもしれませんが、我々が物を見る際、重要な3(あるいは4)要素があります。すなわち「光」「物体」「目(加えて脳)」です。この3(あるいは4要素)があってこそ物は視認され、そしてこの3(4)要素によって「見え方が変わる(あるいは視認できない)」のです。
いかなる物体でも我々が視認している限りは、「物体に光が当たり」、そして「その物体の固有色以外は物体が吸収し、固有色のみが反射」し、そして「物体の固有色が目に届き(さらに脳がそれを認識)」することで初めて人は物体(そしてその色彩)を認知します(このお話しは当ブログの別記事にきちんと書いておりますので、読んでいただけると助かります。^^;)。
おおよそいかなる物体も一見つるつるに見えても、ミクロの目で見て見るとざらざらしています。例えば人間の肌なんかも一見つるっとしていますが、拡大してみると毛穴があり、また決して鏡の面のように一様な面ではないことから、その表面に当たった光が乱反射のようになり、「全ての光を反射する」という形にはならないんですね。
つまり、鏡面のような表面はなめらかで光が乱反射的に屈折しない一様な面である必要があるわけです。
金箔を「磨けば」鏡様になるというのは、その表面がより沢山の光を反射できる程度につるつるに加工できるから、です。これには金箔が「延びる」性質や、(適正技法を用いれば)くっつくべき物体にくっつく性質、(あくまでも適正技法を使用している限りは)物体にくっついた後も展性を失わない性質が関わります。
と、ここまでいうと「金ってすごい!」と思うのですが、これは「金」だけの性質で成り立つものではありません。「金」だけの問題であれば、日本の書物や日本画においても、金箔はきらきらぴっかぴかしていておかしくないのですが、日本の書物や絵画の基底材は紙か布(絹など)で、特に巻子状のものの場合は西洋ほどに金を磨くことが不可能なのです。
では逆説的になぜ紙や布を主体にした本、巻物系(書物、絵巻、掛け軸に関わらず)ではぴかぴかは無理なのか。それは、基底材自体が「柔らかい(しなやか)であること」「凸凹があること」が理由です。
上記のように「鏡」は表面がつるつるであることが必須ですが、紙や布の表面には紙や布を構成する繊維、あるいは糸の織り目があります。それは非常にわずかな凸凹ではありますが、その上にごくごく薄い金箔を張り付けると紙や布の繊維や折り目を拾い上げてしまい、それが金箔に鏡面特性を与えることを阻害するのです(金箔表面が凸凹してしまう)。
ならば!とその表面をつるつるにするために、紙の繊維や布の織目を埋めてしまうほどに下地などを塗布すると、基底材はそのしなやかさを失います。
それの何がいけないのか。巻物や巻子本の場合は「巻く前提」であることで、固い下地を厚く塗布すれば、基底材を巻いたり解いたりするうちに、早々に下地塗布箇所に亀裂が入り、剥落・損失することが約束されます。これは冊子本のようなものでも同じで、基底材がしなやかで柔らかく、その形状を例えば下敷きなどようにキープできない限りは、その上にお煎餅のように固い何かを厚く塗布してしまうと、本をめくる度にその固い塗布部分が剥落していってしまうのです。また、日本画の基底材となるような薄くしなやかな紙や布に対し、硬く厚い何かを塗布すると、基底材のその箇所に負担がかかり、その塗布物のある箇所から基底材が損傷していく危険性もでてきます。
加えて特に巻物がそうですが、「巻く」あるいは「解く」という動作のために、一様な形状を保たない(カールした状態と比較的まっすぐな状態をいききする)ことから、例え張り付けた箔を十分磨くことができたとしても、アルミ箔と同じに、巻いたり解いたりする内に、ぴかぴか感は失われ、鏡面的な表面は結果的に失われてしまうでしょう。
さらに日本の表具(巻きものや本、ふすまなど)を残していく上で定期的な修復は必須ですが、その際に布や紙の基底材上に分厚く固いものがあることは適正な修復を阻害します。修復においても全ての層がしなやかであることが重要なのです(これは私自身が、地元の美術館併設の表具などの修復工房で一年足らずとはいえ研修した経験から断言できることです)。
なんていうんでしょうね。洋の東西に関わらず古くから残っている作品というのは、この「表現として可能だけど、あえてやらない」というのがあると思うのです。
ちなみに紙や布の基底材の上に「分厚く固いものがある」ことは、西洋絵画でも同様によいことではなく、修復の際に困難をもたらすことになるので、正直「自分の作品の寿命は30年でいい(修復しないし、美術館にもその旨を伝えて購入するかどうかを判断してもらう)」くらいの意気込みでそういうことをしてほしいなぁと思っていたりします(苦笑)。奇をてらった作品ほどそうなので、作品を購入する方は気をつけてほしいですね。特に絵具が分厚いほど、洋の東西に関わらず危険物件です(苦笑)。
とはいえ金箔技法において、通常基底材となるのは「木の板」です。そう、紙や布とは違い、硬質な物体となります。適正な基底材としての「板」というのは色々条件があるのですが、この記事ではとりあえずそれは置いておいて、ひとまず金箔を「磨い」て、鏡のようにぴかぴかにしたい!という場合は硬質基底材である木の板を使用するほうが適しています。理由は上述した内容でおそらく推察可能かと思います。
とここからさらに話は続くことが予感されているとは思いますが、本日はすでにここまでに大分長く書いておりますので、中途半端ながら、ここまで。当記事を最後まで読んで下さり、ありがとうございます。また次の記事も読んでいただけますと幸いです。ではでは、また~。





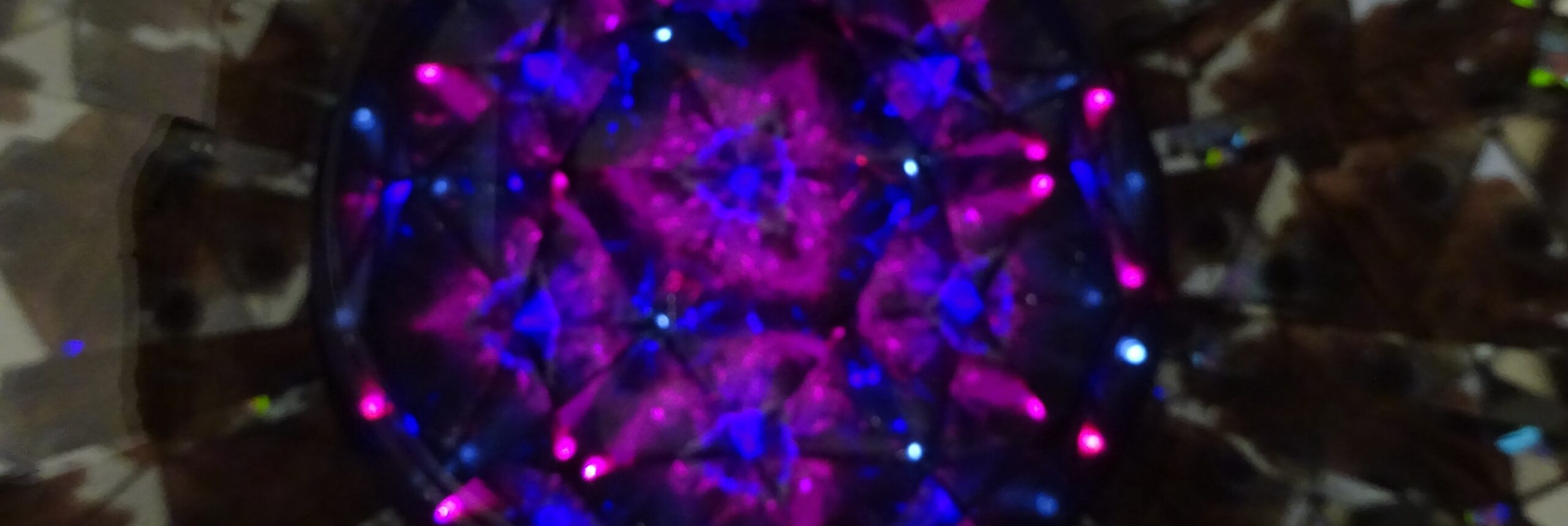


コメント