「金箔のお話⑯:西洋での使用方法・技術④」までにて、一通りの流れを書きましたので、ここからは各種付けたし的な記述を。
「金箔のお話⑬:西洋での使用方法・技術①」にてヨーロッパでは伝統的かつ一般的には「硬い基底材の上」にて金箔を使用していたとお話ししました。木材や、本の基底材である羊皮紙の上などです(羊皮紙はいわばスルメのような硬さなので)。
で、その理由としてここまでのお話しで「A:凸凹した表面に金箔を貼っても鏡面状にはならないため、この凸凹を覆うほどの下地を必要としたから」「B:ただ金箔を張り付けても鏡面様にはならず、【磨く】必要があるから」「C:金箔を貼る上で【接着剤】を使用した場合は鏡面様にはならないため」「D:勿論布や紙などの上に下地などを塗布し、金箔を貼り、磨くことはできるが、美観の保存、作品自体の物理的な保存上向かないため(作品の長期保存上適正ではない)」などの理由をお話ししてきました。
伝統的な作品、何百年と残って生きている作品というのは「今、それが可能だからいいじゃん!」ではなく、「今の美観や物理的な健康が、どれだけ時間を経ても同じに残るように」と考え、またその素材(およびその上下に関わる素材同士の相性など)を知り尽くした上で使われているのだと実感します。
ちなみに金箔を磨くと「鏡面様」になるだけでなく、金箔の一枚一枚の様相が分からなくなるほど金箔面が一体化し、あたかも広い美術作品の背景や額縁などが金の延べ棒から作られたように見えます。これが日本画で見られる金箔使いには見られない美観です。
また、下地に使う体質顔料にもよりますが、パンチングとでもいうのか、革細工に使用するような模様を持つ金属棒を金箔を磨いた上から叩きつけることで文様をつけることもできます。金箔のその「展性」という性質のため、下地などが沈むのに応じて金箔も伸びて、文様のある金の延べ棒のような見た目になります。
あるいは下地段階で細い線状に窪みをつけ、その上からボルスを塗布し金箔を貼る方法もあります(motifs en creux)。こっちはオランダの技法とされており(上記はイタリアの技法)、おそらく使用する下地の素材が違うので、パンチングには向かないため、箔を貼る前に窪みをつけるという方法をとっているのだと思います。これは実際に下地の使い比べをすればすぐわかることですので、気になる方は是非色々お試しください。
上記の窪みをつける方法とは逆に、下地の上に盛り上げるようにレリーフをつけ、その上から金箔を貼る方法もあります(motifs en reliefs)。これなんかは13世紀とかそういった話ではなく、もっと古い時代などからある技法なのでまさに伝統技術ですね。
またこのmotifs en reliefsと関わりのありそうな技法として、宝石、半貴石、象牙などをレリーフに埋めて、下地部分に箔を貼る方法なんかもあります(Incrustations)。
あとはあまり現代の作家さんとかがやらない技法としてsgfaffitoがあります。もともとは壁画技法で、金箔とは関係ないのですが、おそらく多くの現代人が幼い頃にやったクレヨン遊びと同じに、クレヨンを下層と上層で塗りつぶし、上層を削るとそこから下層が見える、みたいな削る技法です。金箔でこれをする場合、鏡面状によく磨いた金箔面の上から色相を一様に塗布し、その色相を文様状に削るのです。日本で見るのはなかなか難しいかもしれませんが、西洋の宗教絵画の背景などで見られる技法です。あとは額縁なんかでも観察できる技法です。実際簡単な技法なので、私が大学で教えていたころは、ゼミの学生に教えてオープンキャンパスに来る高校生にさせてみたりしていました(笑)。
あとは勿論先の記事で書いたミクスチョンを使う技法。油性のいわば接着剤的なものを使用し、細かい文様などの表現として金箔を貼ることができます。壁画なんかで箔を貼る際にもこれを使用します。
最後に別の金属箔の上に金箔を貼ってある種のものを装飾する技法がありますが、これはちょっと特殊すぎるのでまた別の機会があればご紹介できればいいかなと思いつつおります。
なお、この金箔シリーズでお話ししているとおり、実際金箔は100%とはいわずとも金でできているため高価な素材です。だからこそ使える状況や人物は限られていたというのは、特に古い時代ほどそうだと納得できると思います。
特に時代が古いほどにそもそもに美術と関われる人自体「権威」あるいは「お金」があるが必要な要素なはずで、そこに「金箔」の持つ、色彩とは違う「非現実」「色彩を超越した光」というのが宗教的表現と非常に親和性があったんでしょうね。
美術そのものが「権威」と「お金持ち」と親和性が高く、だからこそ「宗教(ここでは教皇や教会と考えるのが正しいかと)」が失墜すると王侯貴族が、そして戦争などで王侯貴族の金銭問題がでてきたり庶民の中でも商人が台頭してくると商人(権威がなくともお金がある:例としてメディチ家。でもメディチ家は教皇も排出しているお家ですけどね)が、と美術を支える人(美術にお金が払える人)、そして美術に描かれるモチーフに変化が出てきます。
ただ、面白いことに「宗教」→「王侯貴族」と有力者が変わったところで、王侯貴族が金箔をじゃんじゃん使ったかというとそうではなさそう。勿論、王侯貴族が絵画を発注する際、教会へ寄進のために発注することがあるので、そこは金箔使用の絵画を発注したのかもしれません。しかし個人的な自画像みたいなもので金箔使っているなーってものってそうみないと思うのですよ。教会と関係性の悪い王族とかでも。
そこがそれでも「宗教」への配慮なのか、あるいは単純に「お金がない」のか、一般的な肖像として金箔が「使いにくい素材」だからなのかは不明ですが、宗教画自体15世紀以降にじゃんじゃん金箔を貼ることは珍しいので、「お金」もそうですけど、それ以降になると基底材の変化など、いろんなことも絡んでくるんでしょうね。
金箔というたった一つの材料のことを考えるだけでも、歴史的にとか、美術史的にとか、技法材料的にとか、いろいろ考えると面白いことがあって、それを総合して考えることが作品を知る方法だということがこういうことで伝わるといいなぁと思いつつおります。
とりあえずまだまだ金箔について書こうと思えば書けるのですが、シリーズとしてはここまで。
本日も最後まで読んで下さりありがとうございます。(ちなみに金箔のお話はもう少しだけ続きます…。汗)ではではまた~。






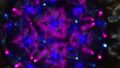

コメント